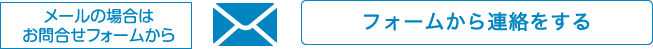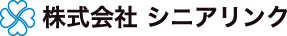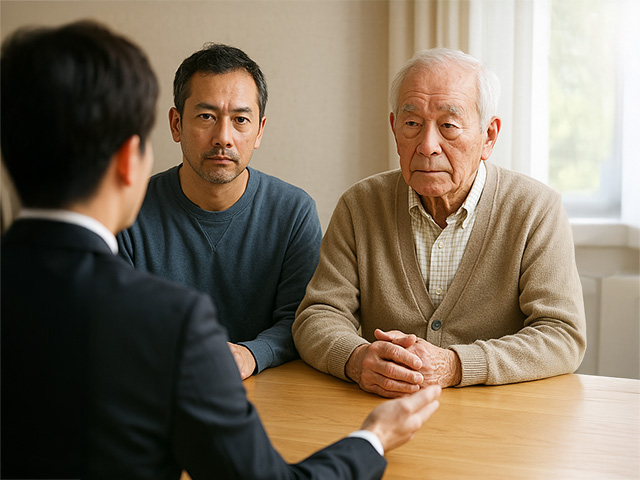
介護施設の利用において介護保険制度の理解は重要です。
詳しいことはご相談いただいた際にご説明いたしますが、概要について解説いたします。
介護保険制度とは
介護保険制度とは、2000年にスタートした公的な社会保障制度であり、高齢者が安心して介護サービスを利用できるように支援する仕組みです。
高齢化が急速に進む中、家族だけで介護を担うことは難しくなり、高齢者が尊厳を持って生活を続けられるよう社会全体で介護を支え合うことを目的に創設されました。
介護保険を利用するには、まず市区町村の窓口で申請を行います。
申請後、市区町村から派遣される認定調査員が訪問調査を行い、医師の意見書と合わせて、要介護認定が行われます。要介護認定は、要支援1~2と要介護1~5の7段階に分類され、認定の度合いによって利用できるサービスの内容や上限額が変わります。
要支援の方には、比較的軽度な日常生活の支援や予防的なサービスが提供されます。一方、要介護の方には、自宅や施設での介護、身体介助、生活支援、リハビリテーションなど、より幅広いサービスが利用可能です。
介護サービス
介護サービスを実際に利用する際には、まずケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族の希望を聞き取り、心身の状況や家庭環境に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。このケアプランに基づき、介護サービス事業者が各種サービスを提供します。
介護保険のサービスは大きく分けて以下の3つに分類されます。
①在宅サービス
訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、福祉用具の貸与など。
②施設サービス
特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院などの介護施設に入所して受けるサービス。
③地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護やグループホームなど、地域での生活を支えるための小規模施設や訪問サービス。
介護保険サービスの費用負担は原則として利用者が1割負担となります。ただし、所得が高い方については所得に応じて2割または3割の負担が求められます。残りの費用は介護保険料と税金によって賄われます。
介護保険料
介護保険料については、65歳以上の方は市区町村ごとに設定された額を年金から天引きまたは直接納付の形で支払い、40~64歳の方は加入している医療保険の保険料に含まれる形で支払います。
給付
実際に介護保険を利用される場合、実のところ要介護認定の内容や利用するサービスにより、給付内容は細かく変わってきます。
このため、介護施設に入居するとどのような給付になるのかは、人により全く異なってしまいます。
結果、親戚や友人知人の話が全く参考にならない事も珍しくありません。
この辺り、制度の理解を難しくしている所ですが、そういった方々も弊社にご相談ください。
入居される方がしっかり理解できるよう専門用語を分かりやすい言葉でご説明し介護保険の不安を解消いたします。
最後に
介護保険法はこれまで7度にわたり改正されています。
今後も改正によって、さまざまな変更がなされることが考えられます。
以前ご家族が利用されていた時の内容と、これから利用される際の内容が異なることもあり得ますので、ご注意ください。